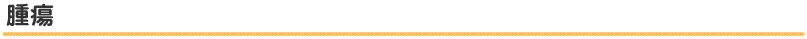
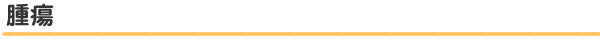
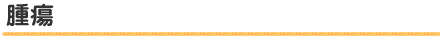
- こんなときは受診を
- 腫瘍科では主に体にできたしこり(腫瘍)を診断、検査していきます。
近年はペットの高齢化も進み、癌の発症率がだんだん上がり、今では10歳の犬の6頭に1頭は、癌にかかるという統計が出ております。
腫瘍には大きく分けて良性、悪性(ガン)があり、悪性の場合には早期発見・早期治療が重要となります。
また中には良性の腫瘍の場合には、動物の負担など考慮し、無理に手術などを行わず、経過をみることもあります。
万が一、ガンや悪性の場合には手術や抗がん剤など治療を行っていきます。
- 腫瘍の症状
 身体にしこり・イボがある
身体にしこり・イボがある
 水を飲む量が急激に増えた
水を飲む量が急激に増えた
 下痢や嘔吐が続く
下痢や嘔吐が続く
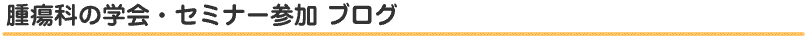
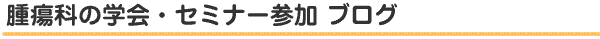
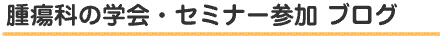
体は1つ1つの細胞からなっています。
細胞はそれぞれの役割を担って統率を取りながら体を維持しています。
この細胞が自分の役割を無視して勝手に行動し、増殖してしまったものを腫瘍といいます。
腫瘍は、腫瘍が発生した臓器や周辺の臓器、あるいは離れた組織や他の臓器に進入(転移)して機能障害を起こします。
重症になると全身の機能低下を招き、死に至ります。
腫瘍は大きく分けて、良性と悪性に分かれます。
直ちに生命に影響を及ぼさないものを良性といい、全身への悪影響と生命への危険が考えられるものを悪性といいます。
ただし、良性腫瘍は腫瘍のできる場所によって全身の機能障害を起こすことや、悪性腫瘍に変わる(悪性転化)ことがありますので注意が必要です。
発生した細胞や組織の種類によって腫瘍は~腫、~癌、あるいは~肉腫と呼びます(~には細胞、組織、器官の名前が入ります)。
一般的に悪性のものは、~癌、~肉腫といい、良性のものは~腫ということが多いのですが、悪性だとわかりきっている腫瘍も~腫と呼ぶことがあります(リンパ腫や肥満細胞腫など)。
たびたび診療室で、原因は?と聞かれることがあります。答えは、わからないことがほとんどです。
なぜなら、その個体に対して大気、紫外線、様々な化学物質、食物、食品添加物、感染症、物理的な刺激などの外からの刺激、生活習慣、そして個体がもともと持っている腫瘍を起こしやすい体質などが複雑に絡みあい影響しあって腫瘍が発生するので原因と思われるものは無数に存在し、1つではないからです。
しかし、動物の場合は犬種や猫種によって起こしやすい腫瘍や病気がありますので、腫瘍に限らず遺伝的にかかりやすい病気について日頃から気に留めておくことは重要です。
治療方針について
-

- 問診
- 腫瘍科では、しこり、イボがどこの部分にあるか、また、「水を飲む量が増えた」など起きている症状が、腫瘍が原因となっている可能性があるため、しっかり問診を行っていきます。
-

- 触診
- しこり、イボを触り、大きさなどを観察していきます。
見た目だけでは良性、悪性(ガン)の確実な見極めはできませんが、しこりのできている場所や大きくなるスピードによって、ある程度、良性か悪性(ガン)どちらの可能性が高いかを判断していきます。
場合によっては、細胞を採取して顕微鏡で観察し良性か悪性なのかを判断していきます。
-

- 治療
- 腫瘍の種類によって、最適な治療方法を話し合いながら決めていきます。
悪性であった場合でも、近年は獣医療が進み、ひと昔のように「治らない病気」ではなく、早期発見・早期治療により完全に治すこともできます。
診断
症状が出ている場合、症状に合わせて血液検査、レントゲン検査、超音波検査、尿検査などを行い異常があるかどうか診断していきます。
無症状であっても、定期検査でわかったり、突然発症して末期だったりすることもあります。
最近では、医療技術の高度化によってMRIやCTによって、従来では診断が困難だった脳や脊髄などの神経系の腫瘍や非常に細かな病変などもわかるようになりました。
これらの検査は腫瘍の存在がわかるのですが、腫瘍が悪性か良性かどうか、あるいは腫瘍の種類は何かといったことまではわかりません。
腫瘍が何であるかは腫瘍の細胞や細胞組織の構築をみることで診断可能です。
この方法には、腫瘍を針で刺して吸引して細胞を見る方法(針吸引による細胞診)、腫瘍の一部を採取する方法(生検)、手術で摘出した腫瘍を検査する方法(病理検査)があります。
針吸引による細胞診は簡便で診断的なことがあるので当院でもよく行ないますが、細胞が取れなかったり、針が届かない深部の場所であったり、そして検査の特性として組織構造がわからないので診断が不可能な場合もあります。
病理検査が最も確実な診断方法ですが、病理検査は通常、手術後の検査となります。
治療
腫瘍が局所にあるならば腫瘍細胞を確実に減少させることができ、かつ完治するために手術は最良の方法です。
良性腫瘍の場合は切除によって完治させることができます。
悪性腫瘍の場合も完全に摘出できれば完治は可能です。
しかし、悪性腫瘍の場合は完全に摘出したと思っていても細胞が残ってしまい、再発や転移をすることがあります。
その場合は、抗がん剤、放射線療法、免疫療法などを組み合わせることにより治療効果の向上が期待できます。
一方、すでに転移がある場合や、摘出することでその生命に著しく不利益(生活の質の低下)になる場合には手術は不向きでしょう。
完治は望めないが、腫瘍そのもので痛みを伴ったり、出血が伴ったりする場合は生活の質の向上を目的に手術する場合があります。
化学療法は、リンパ腫、白血病、形質細胞腫、組織球腫などの血液細胞の腫瘍に対して最も有効で第一選択となります。
しかし、その他の腫瘍では化学療法単独で完治することはできません。
肉眼的に腫瘍とわかる大きさものに対して効果は限定的なので、例えば手術で腫瘍を摘出して腫瘍の存在が肉眼的に確認できなくなってから化学療法を行うというように補助あるいは併用療法として使用します。
腫瘍の種類によって、化学療法が良く効く腫瘍から全く効かない腫瘍まで様々ですので、化学療法は腫瘍の診断に基づいて行ないます。
化学療法=副作用を気にするあまり、化学療法自体を否定的にとらえてしまうことは仕方がないことかもしれません。
化学療法は腫瘍細胞だけに効く薬ではなく、細胞分裂が盛んな細胞《血液細胞(特に白血球)、胃腸の粘膜細胞など》に作用するので、副作用がある治療です。
しかし、動物に化学療法を行なうとき、ヒトとは大きく違って治療期間中は元気でいられることが多く、しかるべき化学療法は化学療法の副作用より腫瘍に対する治療効果の方が上回っています。
化学療法中に起こりうる副作用については以下を参照してください。
・白血球数の減少
血液中にある白血球は外からの侵入者(病原体)に対して闘う細胞です。
化学療法剤の多くは血液細胞(特に白血球)の産生能力を低下させます。
白血球が低下すると免疫力が弱くなり、容易に感染してしまうことがあります。
そのため、化学療法を開始する場合や投与後に調子の悪い場合は血液検査を行い、化学療法を中止あるいは延期したり抗生物質を投与したりします。
・胃腸障害(食欲不振・嘔吐・下痢)
胃腸障害が起こるとするならば通常、化学療法剤投与後2~7日で起こるでしょう。
適切に治療がされれば早期に回復することがほとんどで、入院が必要になることはまれです。
ただ、脱水すると悪心のため、さらに食欲不振・嘔吐・下痢がひどくなり、さらに脱水して・・・と悪くなる一方ですので、具合が悪そうだと思ったら早めに来院していただくことが望ましいでしょう。
・脱毛(抜け毛)
脱毛を心配される方は多いでのですが、動物では通常ヒトのような脱毛は見られません。
脱毛があっても軽度が、あるいは薄毛になる程度で、ほとんどの場合は普段と変わりないと感じられると思います。ただし、ひげは抜けてしまうことが多いです。
放射線は一部の腫瘍に対して非常に高い治療効果があります。
放射線療法は単独あるいは、手術前、手術中、手術後などにも併用して行なうこともあります。
また、手術ができず完治が期待できない症例でも、痛みを少なくさせ生活の質を改善させるために放射線療法を選択することがあります。
放射線療法では、放射線を患部に正確に照射するために麻酔を使用します。
しかも、副作用を減らし治療効果を高めるために、複数回にわたって放射線を患部に照射していきます。
しかしながら、放射線療法を受けられるのは一部の診療施設に限られているので誰でも簡単に治療を受けられるとはいえないのが現状です。
放射線そのものは痛みを伴いませんが、放射線療法の副作用として時間が経過してから照射した皮膚に脱毛や日焼けのような変化が起こることがあります。
また、頭部の放射線を行う場合、眼に当たる場合があります。治療後、数ヶ月以上経過してから白内障や角膜・網膜の障害などが起こることがあります。
腫瘍を構成する異常な細胞は、意外なことに健康な人や動物の体内で毎日のようにつくられています。
通常、その異常な細胞は体内に存在する免疫機構によって認識され、破壊・駆逐されています。
その免疫機構から逃れた細胞が増殖して腫瘍になります。
免疫療法は自分自身が本来持っている腫瘍細胞と戦うための免疫機構を強化する方法です。
自分の免疫細胞を培養・増殖させて投与する方法(活性化リンパ球療法)、インターフェロン療法、サプリメントなど様々な方法があります。
これらの療法では副作用が少ないことはとてもいいことなのですが、効果が弱かったり、一定でなかったりするため、単独使用だけでなく他の療法と併用する補助療法として用いることができます。

液体窒素を使った治療で、その場で処置が出来ます。
このペン型の機器はクリヨペンといいます。
先端から液体窒素が噴出されるもので、体表の小さなイボを凍らせます。人の皮膚科でもイボを液体窒素で焼いてもらった方もいるかと思いますが、それと全く同じです。
以前はイボでも手術か局所麻酔が必要で切除しなければならなかったのですが、これがあれば無麻酔で数分で終わりです。小さいものでは1回のみで終了しますが、大きいものでは数回にわたって凍結する場合もあります。
皮膚の深部のものや大きいものは適応外ですが、皮膚の表面、目の縁の腫瘤、耳の中の腫瘤にも有効です。見た目には気になるけど、手術をしたくない人にお勧めです。
腫瘍の一部
動物には非常に多くの種類の腫瘍が発生します。以下によく見られる腫瘍の一部を解説します。
乳腺由来の腫瘍を乳腺腫瘍といいます。
良性のものは乳腺腫、乳腺混合腫瘍などがあり、悪性のものは乳癌や炎症性乳癌などがあります。
乳腺腫瘍は雌の動物に最も発生する腫瘍です。
この腫瘍は、卵巣からの性ホルモンに関連しています。
早期に避妊手術を行うことによって発生率が変わります。
犬では初回発情前の避妊手術で0.05%、1回発情後では8%と予防効果がありますが、2回目以降では26%と高率になり予防効果がなくなります。
猫では1歳以上になると予防効果がありませんので、避妊手術を行う時期は1歳未満で卵巣ホルモンの影響を受けていない初回発情前が理想的です。
犬の乳腺腫瘍は、50%が良性で50%が悪性といわれています。
猫の乳腺腫瘍は80~90%が悪性で進行が早いので、腹部にしこりを見つけたらすぐに受診しましょう。
治療は手術が第一選択となります。
化学療法(抗がん剤)はある程度有効ではありますが、目に見えないほどの病変でない限り有効とはいえないでしょう。
化学療法の使い方としては、術後に腫瘍細胞の取り残しや転移が予想された場合に使用するのが理想的です。
当院では、手術前にレントゲン検査などによる画像診断を行い、腫瘍が転移していなければ手術を行います。
再発率の低下や寿命の延長が期待できることから、同時に避妊手術をすることをお勧めします。
良性の場合は完全に摘出してしまえば完治となります。
悪性の場合は、前述のように化学療法や免疫療法をお勧めすることがあります。
まれに見られる炎症性乳癌は例外的に手術が第一選択となりません。
犬や猫でよく認められる悪性疾患です。
リンパ腫は、リンパ肉腫や悪性リンパ腫と呼ばれることがありますが同じものです。
全身を巡っているリンパ系組織が腫瘍化したものの総称で、種類や発生した部位によって治療法が異なることがあります。
症状は多種多様で、全身のリンパ節が腫れる多中心型リンパ腫は、発熱、元気食欲の消失、体重減少などの症状が認められます。
胃腸に発生する消化管型リンパ腫は嘔吐、食欲不振、下痢、下血、体重減少などがみられます。
胸腔内に発生する縦隔型リンパ腫は、発熱、元気食欲の消失、体重減少に加えて呼吸困難や不整脈、虚弱なども起こすことがあります。
眼、神経、腎臓あるいは心臓などにできる節外性リンパ腫や、皮膚にできる皮膚型リンパ腫もあり、症状はできた部位によって様々です。
リンパ系組織は全身を網の目のように分布しているため、通常は化学療法が第一選択となります。
多くのリンパ腫は化学療法に対してよく反応します。治療によって腫瘍細胞が確認できなくなった状態を寛解といいますが、完全に腫瘍がなくなったこと意味しているわけではありません。
リンパ腫の治療はこの寛解期間をどれだけ維持できるかが重要となります。
多中心型リンパ腫では複数の抗がん剤を投与する多剤併用療法が有効であったり、消化管型リンパ腫では最初に手術によって病変を摘出し次いで化学療法を行ったり、あるいは節外性リンパ腫では放射線療法を第一選択する場合もあります。
現在の獣医学では、いずれの治療法でも完治にいたるのは難しいです。
しかし、リンパ腫は抗がん剤によく反応する腫瘍です。1年以上生存することはまれではありません。
たった1年しか…と思うかもしれませんが、犬や猫にとっての1年は人の4年に相当します。そして一旦寛解すると、化学療法期間中、患者は元気でいることがほとんどです。
名前はかわいらしいのですが犬猫に発生する腫瘍で、犬では特に悪性です。太っていることと腫瘍は関係ありません。
血液細胞の一種である肥満細胞が腫瘍化したもので全身のどこにでもできます。
治療は手術が第一選択となります。
この腫瘍は転移や再発が多いので手術時には健康と思われる組織も含めてできるだけ広範に摘出しなければなりません。
手術による完全切除が完治できる最良の方法です。
部位によっては十分に摘出できないことがあります。
十分に摘出できなかった場合や摘出困難な場合は、ある種の抗がん剤、ステロイド剤、インターフェロンの投与や放射線療法などの治療法を選択する場合があります。
メラニン色素を作るメラノサイトが腫瘍化したものです。
皮膚にできるメラノーマは良性のことが多いので、手術によって完治が可能です。
頭部(口腔、鼻腔、眼)や肢端(爪の基部や指先)にできるものは悪性のことがほとんどです。
急速に増大したり、転移したりすることが多く、気がついた時点で肺に転移していることもまれではありません。
悪性の場合も手術が第一選択となり、健康と思われる組織も含めてできるだけ広範に摘出します。
例え手術時に転移が認められなくても、術後に抗がん剤の投与や消炎鎮痛剤を投与することで寿命が延びる可能性があるのでお勧めすることがあります。
骨にできる最も多い悪性の腫瘍ですが、まれに骨と無関係な組織にもできます。
大型犬や超大型犬で発生率が高く、猫ではまれです。
きわめて転移しやすい腫瘍のため、診断時にすでに肺に転移していることがあります。
罹患したほとんどの場合は完治困難なため、痛みの緩和と生存期間を延長することが治療の目的となるかもしれません。
治療として手術、化学療法、放射線、鎮痛剤の投与などが行われます。
血管内皮細胞が腫瘍化したもので、悪性で転移しやすい腫瘍です。
血管のある場所にできる可能性がありますが、とくに脾臓、肝臓、心臓あるいは皮膚にできることが多いです。
中高齢の大型犬で発生が多く、シェパードやレトリバーは注意が必要です。
脾臓や肝臓にできた腫瘍は外見ではわからないため、お腹の中の腫瘍が突然破裂して出血死することがあります。
このため、特に大型犬では定期的な検診で腹部の超音波検査をするとよいでしょう。
手術で取り除くことが最良ですが、転移しやすい腫瘍ですので手術後も注意が必要で悪いことが多いです。
現在のところ化学療法は、多少効果がある程度か、あまり奏功しないとされています。
膀胱に腫瘍ができると血尿、排尿困難、頻尿などの症状が認められます。
これら症状は膀胱炎、膀胱結石、尿路結石などでもみられますので超音波検査やレントゲン検査で鑑別します。
膀胱にできる腫瘍では平滑筋腫や乳頭腫などの良性のものがありますが一般的に悪性のものが多く、扁平上皮癌、平滑筋肉腫などがあり、最も多いのが移行上皮癌です。
この移行上皮癌は、膀胱以外にも腎臓、尿管、尿道、前立腺にできることがあります。
老齢の雌犬に多く、特にシェルティーでは多いようです。猫は膀胱の腫瘍は比較的まれです。
治療は、摘出が可能なものは手術が第一選択になります。
移行上皮癌は尿管と尿道と膀胱が接続する膀胱三角という領域に腫瘍を形成することが多く、手術が困難か不適応のことがあります。
腫瘍が大きくなり、膀胱を摘出して尿管を腸に接続する尿路変更手術がありますが、感染や便失禁などの合併症が起こりやすくなります。
摘出が不可能な場合や転移がある場合は非ステロイド性の消炎鎮痛剤や抗がん剤が有効なことがあるので投与します。
副腎は外側にある皮質と呼ばれる部分と、内側にある髄質と呼ばれる部分があります。
皮質が腫瘍化した場合と髄質が腫瘍化した場合では、同じ副腎腫瘍でも症状が違います。
副腎皮質が腫瘍化した場合は、良性のことも悪性のこともありますが、コルチゾールを放出して副腎皮質機能亢進症を引き起こします。
副腎皮質機能亢進症はクッシング症候群とも呼ばれ、脳にある下垂体の異常によってもおこります。
たくさんお水を飲み大量のおしっこをする(多飲多尿)、多食、腹部膨満、虚弱、脱毛などの症状がみられます。
副腎腫瘍が摘出可能であれば手術で摘出するのが最良です。
手術が困難な場合や腫瘍の転移が認められる場合は、コルチゾールを分解する薬や副腎皮質の細胞を破壊する薬の投与を行います。
副腎髄質が腫瘍化した場合は褐色細胞腫(クロム親和性細胞腫)と呼ばれます。
副腎髄質からはカテコールアミンという物質が産生されます。カテコールアミンは血管を収縮させ、心拍数を上昇させます。褐色細胞腫は、カテコールアミンを大量に放出するために高血圧や不整脈を引き起こします。
このため、虚脱、食欲不振、呼吸速迫、呼吸困難、嘔吐、体重減少などの症状がみられます。
転移した腫瘍によって血管が閉塞され後ろ足や下半身がむくむことがあります。
手術で摘出するのが最良ですが、手術前から手術中そして手術後に至るまで不整脈の出現や血圧の変動が起こりやすくとても危険が伴います。
 身体にしこり・イボがある
身体にしこり・イボがある 水を飲む量が急激に増えた
水を飲む量が急激に増えた 下痢や嘔吐が続く
下痢や嘔吐が続く



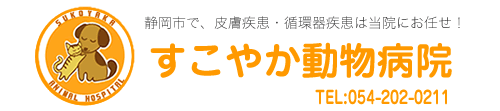

 サイトマップ
サイトマップ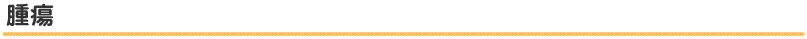
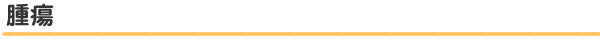
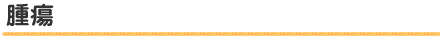
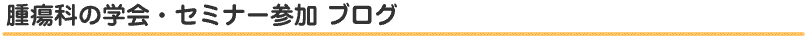
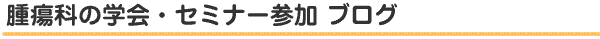
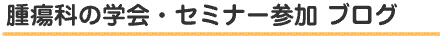
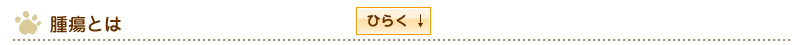
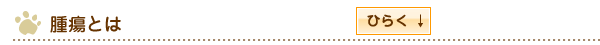
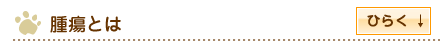
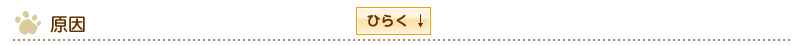
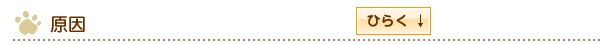
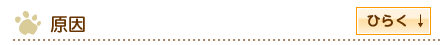
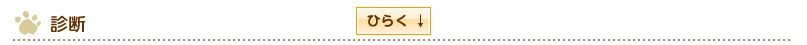
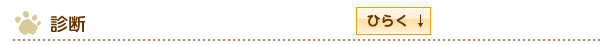
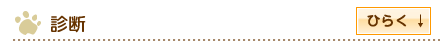
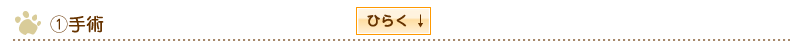
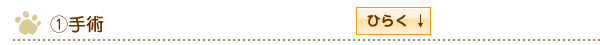
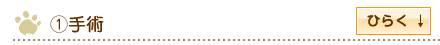

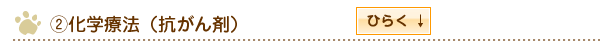


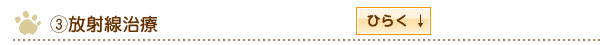
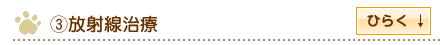

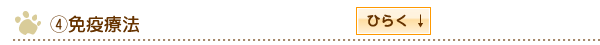
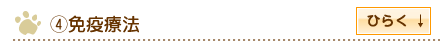
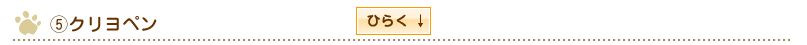
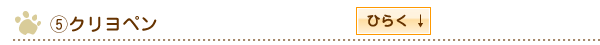
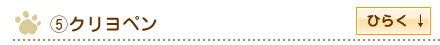


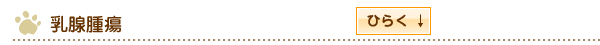
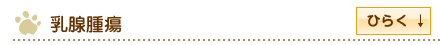

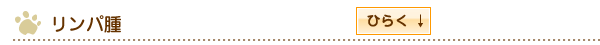
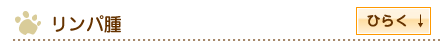
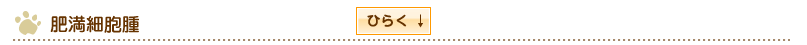
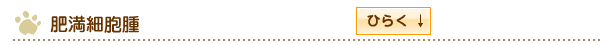
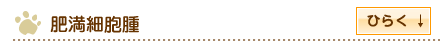

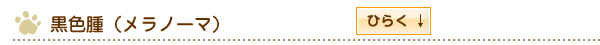


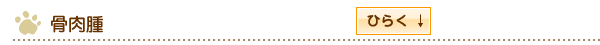
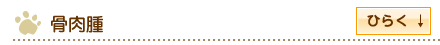

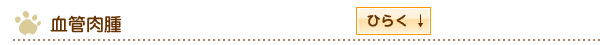
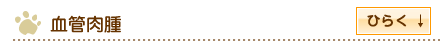

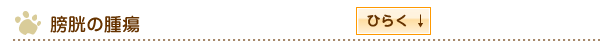
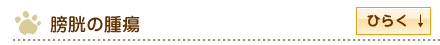

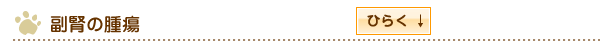
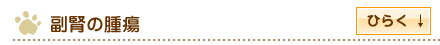


 元気・食欲がない、いつもと様子が違う
元気・食欲がない、いつもと様子が違う